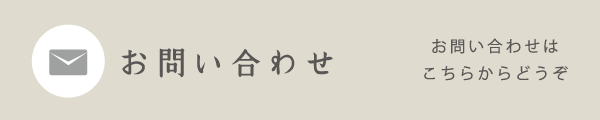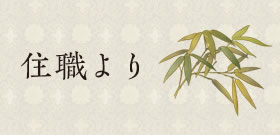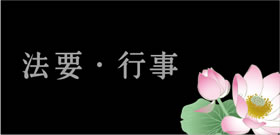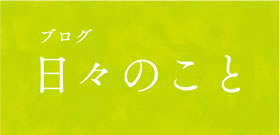温泉津とは

温泉津とは

温泉津と書いて「ゆのつ」と読み、「ゆ」は文字通り温泉を指し、「津」は港を意味します。つまり「ゆのつ」とは“温泉と港の町”を表しています。
温泉の歴史は永く、1300年前の開湯と伝えられ、手負いの狸が入浴しているのを旅の僧が見つけたことが温泉の発見に至ったという説や、大国主命が病の兎を湯に入れ救ったことが始まりであるという説など、温泉発見については諸説あります。
また、港は16世紀後半には港町が出来始め、江戸時代には<>銀山奉行支配の幕府直轄領となり、17世紀初頭までは石見銀の積出港として繁栄しました。その後北前船による廻船業の基地として利用され多くの人々がこの地を訪れ、温泉や宿を利用し大いに賑わいました。
世界遺産としての温泉津

温泉津温泉は平地が少ないという地形的な点で大きな開発がされず現在に至り、昔のままの街並みが残っています。平成16年に温泉街としては初の『国の重要伝統的建造物群保存地区』に選定され、さらに平成19年7月には『石見銀山遺跡とその文化的景観』として温泉津の町が世界遺産に登録されました。